ギチリ、と嫌な音が聞こえる。強く握られた右の手首が啼いているんだと思った。其の内、手首から上が、ふるふる、小刻みに震え出す。怒りだ、これはきっと怒りだ、血の流れを無理矢理止められたことに、私の心臓が怒っているんだ
「柴山は、なにがしたいの」
私の右手首を渾身の力で握り締める男。何度も繰り返されるこの行為に、答えが必要となった訳ではない、この男の考えを知りたいわけでもない、ただ私は早く家に帰りたいだけ、それだけ、それだけ、
「もっと三島を傷つけたい」
「なにそれ、私を傷つけて楽しいの」
「楽しくない、全然楽しくない」
跳ねない声、それでいて地を這うようでもない、心臓の少し横をするりと抜けていく柴山の声
打ち抜くのなら打ち抜けば良い、貫くのなら貫けば良い、掠めるだけは少し悲しい、
「わからない」
「本当は傷つけたいわけじゃない」
「本当はなにがしたいの」
少し怒ったように聞けば、するり、離れる男の左手
「三島に傷つけられたい」
塞き止められていた血が勢いづきながら右手へ流れていく、ドクドクと血の流れる音がした
「このエム野郎」
「三島に、傷つけられたいんだよ」
挑戦的な声でおかしなことを言いながら自虐的な笑みを浮かべているのに、何故この男はこんなにも泣きそうなのか、何故泣き出してしまいそうな瞳で私を見ているのか、知ってしまえばきっと戻れない、
知りたくない?違う知ることが出来ないんだ、知りたくないの一言で真実を拒絶する力なんて私にはない。私の意思の介入が許される領域に、真実という存在はない、圧倒的に、絶対的な、言葉なんかで表現できるはずないそんな場所こそ、相応しい
「私を傷つけたいって言ったくせに」
「三島にも傷を負って欲しい、出来れば俺と同じ傷」
「柴山は変態だね、変態め」
届かない言葉、届かないと知りながら続ける会話、いったい何を生むのだろう、言葉を無駄遣いして、私たちは何を残したいのだろう、言葉の跡は所詮消えてしまう、其の儚さを教えてくれるだけ、なのに
無限の組み合わせが何を生むというの、何を、私たちの元に残すというの。解らない解らない、でも解らないのはきっと至極当然のこと、考えているようで考えていない私たち、熱を発しているのは脳ではなくこの手首、
「でも柴山好き」
うそつき、ほらほら、なにも生まれない
「俺も三島好き」
うそつき、うそつき、君の言葉は届かない
「だから、俺のこと傷つけて、そして、傷ついてよ三島」
「無理」
「知ってる」
なにをしっているの、なにをしっているというの、
「私が傷ついてから、柴山を傷つけるのと、どう違うの」
「残る傷は同じだから、どっちも変わらないよ」
「傷ついてから傷つける、傷つけてから傷つく、柴山はどっちなの」
「俺は傷つきたいから三島を傷つける」
ニヤリよりもっと酷くて、汚くて、直視できない、笑みなのか解らない難しい顔でサラリとそんなことをいってのける。此れほどゴチャゴチャした顔を出来るのは、きっと柴山だけだろう、
「柴山のエム野郎」
「決してエムではないが、変態なのは否めない」
「気持ち悪い、でも柴山好き」
「お前も結構エム野郎かもよ、でも三島好きだ」
「知ってる」
しっている、きみも、わたしも、嘘ばかりをしっている
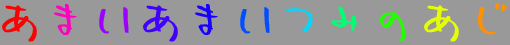
|